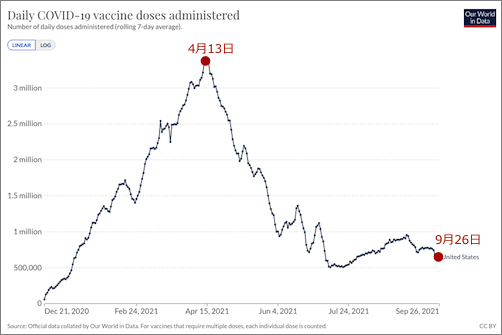異次元緩和の帰結 絵空事ではない「日銀破綻」 預金通帳の「紙くず」リスク=藤巻健史
エコノミスト 2021/09/27
現在1ドル=110円前後で推移するドル・円相場について、筆者は「円安」だと認識していない。国力に比べて、かなりの「円高」だと捉えている。日本はこの40年来、「世界の主要国で断トツの低成長」であり、その原因は円が日本の実力に比べて強すぎたことにある。(安い日本)
だが、「国力に比べて強すぎる円」は近い将来、暴落し、制御不能なインフーションに陥る「ハイパーインフレ」を招くと考えている。現在の日本円は無価値となり紙幣や預金通帳は、ただの紙くずになってしまうだろう。
ハイパーインフレの真因
通常の「インフレ/デフレ」は、商品やサービスの需給関係によって起きるが、ハイパーインフレ発生のメカニズムは通常の需給では説明できない。それは、中央銀行の信用が失墜し、通貨の信認が失われる事態により発生する。中銀の信用失墜は、中銀が債務超過に陥るといった、財務内容の健全性が失われることによって起きるのだ。
そのような事態を避けるため、「通貨の番人」たる矜持(きょうじ)を忘れなかったかつての中銀は、価格が大きく下落する可能性のある金融資産を決して保有しなかった。
ところが、今の日銀は上場投資信託(ETF)に買い入れを通じて日本株の「最大の株主」になっている。また、保有国債の大部分は償還期限10年の長期債(21年7月末で534兆円中、504兆円保有)だ。世界の主要な中銀で、金融政策目的で株式を保有しているのは日銀だけであり、バランスシート(貸借対照表、総資産約723兆円)に対して長期国債をこれほどまでに保有しているのも日銀だけである。中短期の国債に比べても同じ幅の金利上昇、例えば1%であっても長期債のほうが値段の下落幅が大きくリスクが高い。
財政ファイナンス
中には「中銀が債務超過になったら、政府が資本補てんすればいい」という識者がいるが、とんでもない暴論だ。もしそのようなニュースが世界に流れたら、その途端に円の売り浴びせが起こり、日銀には対抗手段がない。日本政府は毎年、歳出が税収を大幅に上回る財政赤字が続いており、国民から徴収した税金で、失われた日銀の信認が回復できるような資本注入ができないからだ。
そもそも日本の財政状況は、公的債務残高が国内総生産(GDP)比で237%(2020年)と、ワースト2位のイタリア(同133%)と比べてもG7(先進7カ国)の中で突出して悪い。この状況を13年3月に就任した黒田東彦総裁と日銀執行部が、「異次元緩和」という名のもと、実質的な「財政ファイナンス」を開始し、財政破綻の危機を先延ばしにした。
財政ファイナンスとは、「中央銀行が通貨を発行して国債を引き受けること」で、財政法5条で禁止されている。現在の日銀は市中から国債を買い入れており、直接引き受けではないとしている。黒田総裁は記者会見などで異次元緩和が「財政ファイナンスではない」と繰り返し説明している。とはいえ、発行中の国債の53%も日銀が保有する現状は、実質的な引き受けであり、財政ファイナンスと言わざるを得ない。
異次元緩和の結果、日銀は資産に計上する国債と、負債側の日銀当座預金残高を急増させた。巨額に保有する国債の保有利回りは、20年度下半期で0・199%と0・2%を割っている。米国債では一晩で動くような幅で上昇すれば、評価損が発生してしまうし、評価損もまた巨額となりうる。日銀は、国債は満期まで持つ目的で保有し、時価評価する必要がない「償却原価法」で評価しており、「評価損は発生しない」と説明している。だが、肝心なのは日銀の自己認識ではなく、外部からの評価だ。外資系金融機関の審査部は、取引先の財務内容を常に時価会計で評価する。
日銀法で「物価の安定」を義務づけられている日銀は、国内でインフレが進行すれば、短期政策金利を引き上げねばならないが、現状では日銀当座預金への付利金利の引き上げしか方法はない。539兆円もの巨額の日銀当座預金残高に付利すれば、1%ごとに5・39兆円もの金利支払い増となる。20年度の日銀の純利益が約1兆4500億円で、損失に備えるための引当金勘定等が10・8兆円しかないのだから、政策金利を引き上げれば赤字決算となり、債務超過に陥りかねない。
日銀が債務超過になれば外資は撤退するだろう。日銀口座に資金残高を置くことが本部から禁止される。これは致命的だ。日本は国内で保有しているドル以外に、新たにドルを獲得する手段がなくなることになるからだ。ドルに交換できない通貨など世界中の誰もが受け取らなくなる。
米長期金利がトドメに
筆者が今、注視しているのは、米長期金利の動向だ。米国が資産価格の上昇継続による資産効果で、日本のバブル期のような狂乱経済(1985~90年)を迎えれば、米国の消費者物価指数はかなりの上昇をするだろう。バブル当時の日本には、強烈な円高進行(84年末1ドル=251・58円、87年末は同122円)というすさまじいデフレ要因が存在したが、今の米国にはそうした歯止めとなる要素がない。
米長期金利が上昇すれば、日米長期金利差拡大でドル高・円安が進行する。エネルギーや食料価格などの輸入物価が上がり、長年デフレが続いてきた日本も、いよいよインフレが避けられなくなる。それでも、日銀は利上げという政策手段を「開封」することができない。債務超過になってしまうからだ。
必死に長期金利上昇を抑えようとするだろうが、その場合、物価はとどまることなく上昇してしまう。悪性インフレの進行だ。もし日銀が長期金利を抑えきれなければ債務超過となり、円が大暴落すると同時に、ハイパーインフレが現実味を帯びる。今まで日本、日銀に本格的な通貨危機が起きなかったのは、ひとえに景気低迷が続き、金利を上げる必要がなかったからに過ぎない。
新中銀しかない
インフレを抑える能力のない日銀は、すでに中銀の体をなしていない。悪性インフレ鎮静化の過程で日銀は廃止され、新しい中銀を創設せざるを得ないだろう。第二次世界大戦後のドイツで、ハイパーインフレ収束のために、かつての中銀ライヒスバンクが廃止され、健全な債務内容の新中銀ブンデスバンクが作られたのと同じ道である。
![[帯状疱疹に悩む人が急増、要因は]という報道](https://nofia.net/wp-content/uploads/2021/09/bnt162b-mrna-codon.jpg)