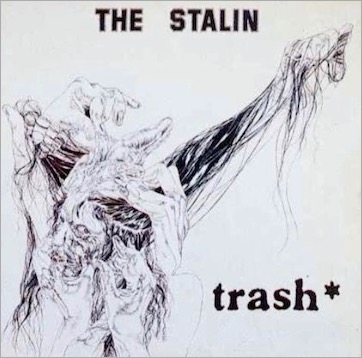カセットも売れてんのか…。カセットは 40年前でもマイナーな存在で、確か少年ナイフというバンドの「みんなたのしく少年ナイフ」を持っていたような気はしますが、当時でも、あまり購入するものではなかったですね。
2025年の英国 レコード売上は18年連続増 カセットテープは53.8%増 オアシスのアルバムの売上が100万枚を超える
amass.jp 2025/12/31

英国レコード産業協会(BPI)の年次報告書によると、2025年、英国のアナログレコードの売上は前年比13.3%増の760万枚に達しました。18年連続の増加を記録しています。
ストリーミングは現在、英国の音楽市場全体の89%を占めており、アルバムは1億8900万枚相当聴かれていますが、ストリーミングは前年比5.5%増ですので、レコードが成長率では大きく上回っています。
この年次報告書によると、2025年、英国のアルバムの総売上は2024年から4.9%増加し、販売・ストリーミングは2億100万枚に達しました。11年連続で増加です。
CDの売上は7.6%減の970万枚。一方、カセットテープはその関心の高まりにより、売上は53.8%増の164,491本に達しています。全体として、フィジカル・アルバム(CD、アナログレコード、カセットテープほか)の売上は1.4%増の1760万枚でした。
BPIはまた、女性アーティストたちが年間を通じて2025年の英国の音楽業界を牽引したと報告。特にテイラー・スウィフトは席巻で、2025年リリース作『The Life of a Showgirl』のレコード売上は14万7000枚を記録。これは1990年代にオフィシャル・チャート・カンパニーがチャート集計を開始して以来、個人アーティストとして最多の記録です。
オアシスも大きな復活を遂げ、再結成ツアーのおかげで、2025年内のアルバムの売り上げが100万枚を超えました。バンドのベスト・アルバム『Time Flies』は2025年に4番目に売れたアルバムとなり、『(What’s The Story) Morning Glory』は7番目に売れたアルバムとなりました。